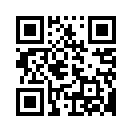2010年10月07日
高島屋百華展
京都市美術館で開催されている「高島屋百華展」を見た。

第一の目当ては、チケットにも用いられている、「アレ夕立に」である。
作者は、もちろん竹内栖鳳。
意外にあっさりとした描き方であった。
「図録」によると1909年の作。文展に出品されている。
「栖鳳がかねてから望んでいた、人物モデルを使って写生を行い本画を仕上げる、という試みがはじめて具現したもの」
と解説されている。
「図録」にはスケッチや写真も載っていて大変興味深い。
また、吉中充代が「図録」のために書いた「総論」
「近代日本の百貨店と美術 ― 高島屋史料館コレクションをみる」
も面白い。
そこで、吉中がふれている
「アレ夕立に」と「絵になる最初」の関係の意味もなるほどという感じ。
「アレ夕立に」では、衣装の柄に対するおもきは大きくなかったのに対して、
「絵になる最初」では、下絵段階からのちに「栖鳳絣」とされる柄が入っていたという。
高島屋の販売戦略とある種の関係があると、読み取れるわけだ。
なるほど、なるほど。

かなり見ごたえのある展覧会だ。
ただ、あまり若い人がいないのは残念。

第一の目当ては、チケットにも用いられている、「アレ夕立に」である。
作者は、もちろん竹内栖鳳。
意外にあっさりとした描き方であった。
「図録」によると1909年の作。文展に出品されている。
「栖鳳がかねてから望んでいた、人物モデルを使って写生を行い本画を仕上げる、という試みがはじめて具現したもの」
と解説されている。
「図録」にはスケッチや写真も載っていて大変興味深い。
また、吉中充代が「図録」のために書いた「総論」
「近代日本の百貨店と美術 ― 高島屋史料館コレクションをみる」
も面白い。
そこで、吉中がふれている
「アレ夕立に」と「絵になる最初」の関係の意味もなるほどという感じ。
「アレ夕立に」では、衣装の柄に対するおもきは大きくなかったのに対して、
「絵になる最初」では、下絵段階からのちに「栖鳳絣」とされる柄が入っていたという。
高島屋の販売戦略とある種の関係があると、読み取れるわけだ。
なるほど、なるほど。

かなり見ごたえのある展覧会だ。
ただ、あまり若い人がいないのは残念。
Posted by 愚華 at 15:37│Comments(0)
│観る